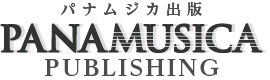Composer
Ruben Garcia-Martin
1983年スペイン西部のサモラ出身。サラマンカ高等音楽院でアレハンドロ・ヤグエに作曲を師事。彼の作品はスペイン国内、ドイツ、イタリア、コロンビア、南アフリカ等、世界中で広く演奏されている。作曲コンクールへも積極的に出場しており、2009年にはトマス・ルイス・デ・ビクトリア国際ポリフォニーコンクールで3位入賞を果たした。 また、ドキュメンタリー映画の劇伴音楽の作曲、スペインのエドゥアルド・マルティネス・トルネル高等音楽院作曲学・音楽理論講師等、活動範囲は幅広い。
Kentaro SATO(Ken-P)
1981年生まれ。静岡県浜松市出身。高校を卒業後、渡米。サンタモニカ・カレッジにて映画と音楽の学位を取得後、カリフォルニア州立大学ノースリッジ校にてメディア作曲科で学士、および大学院合唱指揮科で修士を修得。 米国ロサンゼルス・ハリウッドで学んだ作編曲家として、米国のオーケストラのみならず、ロンドン管弦楽団、シドニー管弦楽団といった世界中のアンサンブルと共演をしながらTV・映画・ゲーム音楽を始め様々なジャンルに音楽を提供する。合唱の分野では、自作ミサ曲のバチカン市国での演奏、国民文化祭合唱部門への委嘱作品など宗教曲・世俗曲に両面において高い評価を受ける。 その他、指揮者・指導者として国内外でのゲスト指揮、指導やワークショップを行うと共に、音楽ハード・ソフトの制作や録音原盤制作や仲介やディレクション、芸術および国内外の法律や知的著作物関連の書籍出版、作詞、日本語および英語ナレーションなど、多方面で活躍している。 ニックネームはKen-P(ケンピー)。どの言語圏の人にもすぐに覚えてもらえ便利。
Sebastian Androne-Nakanishi
1989年ルーマニア出身。数々の賞を受賞した作曲家であり、彼の作品は演奏会用の現代音楽から演劇・映画音楽にまで多岐にわたる。 2014年にはオーケストラ作品で「ジョルジェ・エネスク賞」、2015年には声楽アンサンブル作品で「TENSO若手作曲賞」、2018年にはスティーブ・カッツが製作したアニメーション「Happiness」へのオーケストラによる劇伴音楽で、チューリッヒ映画祭にて最優秀賞「ゴールデン・アイ」など、さまざまな最優秀賞を受賞。 作曲をルーマニア、イギリス、フランスで学ぶ。ブカレスト国立音楽大学にてダン・デデュに作曲を長年師事し2018年博士号を取得。 エラスムス奨学金を2度取得し、修士課程をバーミンガム音楽院、博士課程をパリ国立高等音楽院において学ぶ。現在はスイス・チューリッヒ芸術大学にて商業音楽を学び、二つ目の修士号取得を目指す。 彼の作品は、ディオティマ弦楽四重奏団(フランス)、BBCシンガーズ(イギリス)、チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団(スイス)、上海フィルハーモニー管弦楽団(中国)など世界中の楽団で演奏されている。
Akira MIYOSHI
1933年東京生まれ。 3歳の頃から自由学園の「子供ピアノ・グループ」でピアノ、ソルフェージュ、作曲を学び、小学校に入った頃から平井康三朗に作曲とヴァイオリンを師事した。 1951年東京大学文学部仏文科に入学。在学中の53年、「ソナタ」が第22回日本音楽コンクール作曲部門第1位、54年「ピアノと管弦楽のための協奏交響曲」が第3回尾高賞、文化庁芸術祭奨励賞を受賞し注目される。 55年給費留学生としてパリ音楽院に留学、アンリ・シャラン、レイモン・ガロワ・モンブランに師事。アンリ・デュティーユの影響も受ける。 57年帰国、東京大学に復学し60年に卒業。この頃から毎年のように大作を発表しており、管弦楽、室内楽、歌曲などのほか、多くの合唱曲がある。 95年から98年まで「夏の散乱」、「谺つり星」、「霧の果実」、「焉歌・波摘み」と毎年オーケストラ作品を発表、「焉歌・波摘み」では自身6回目の尾高賞を受賞した。 99年3月には初めてのオペラ<支倉常長「遠い帆」>を発表、その成果により第31回サントリー音楽賞を受賞。 1974年~95年まで桐朋学園大学学長を務める。 99年12月芸術院会員となり、2001年11月文化功労者に選ばれる。 2013年10月没。
Susumu HAMASAKI
国立音楽大学作曲学科卒業、同大学院作曲専攻作品創作コース修了。作曲を故・溝上日出夫、故・増田宏三、楽曲分析を福士則夫、和声・対位法を小河原美子の各氏に師事。現在福島県の高等学校音楽教員を務める。各種大会や演奏会にて吹奏楽、合唱作品を多数発表。県内の中学校、高校からの委嘱作品も多数作曲している。編曲作品も福島楽友協会合唱団委嘱による「あの頃のうた」シリーズ(Part1〜4)をはじめ多数発表している。 またジャズピアニストとしての活動も行なっている。 平成27年度合唱組曲公募・第26回朝日作曲賞佳作。出版楽譜「3つのマリア讃歌」(パナムジカ刊)
Gabriele Taschetti
1993年イタリア出身。若手作曲家、音楽学者として活躍中。 パドヴァ音楽院で作曲を学んだ後、パドヴァ大学で音楽学の博士号を取得。 合唱団員として長年の経験をもつ。普段は主に古代音楽と声楽曲に興味をもち、活動を行っている。
Ko MATSUSHITA
1962年東京生まれ。作曲家、合唱指揮者。国立音楽大学作曲学科首席卒業。卒業後、ハンガリーに渡り、合唱指揮法及び作曲法を学ぶ。レメーニ・ヤーノシュ、モハイ・ミクローシュ他に師事。 作曲家として生み出している作品は、合唱曲を中心として多岐にわたり、それらの作品は世界各国で広く演奏されており、同じく楽譜も、国内外で出版が相次いでいる。これまでに、国内およびポーランド、中国、台湾において個展が開催された。深圳では深圳交響楽団によりオーケストラ作品の初演も行われた。 同時に、東京合唱アライアンス〈耕友会〉芸術総監督として12団体の指揮を務め、各合唱団は精力的な活動を繰り広げ、ヨーロッパの数々の国際合唱コンクールにおいて、グランプリ等優秀な成績をあげている。耕友会以外では、国内で3団体の常任指揮者、海外では中国・北京大学学生合唱団の客演指揮者に就任しているほか、各国の合唱団の客演指揮者として招聘されている。 2015年6月より、八王子市で発足した児童合唱団「みなみ野キッズシンガーズ」の芸術顧問・音楽監督および指導者を務め、地域の子ども達の音楽教育にも注力している。 2005年、合唱音楽における国際的かつ優れた活動が認められ、「ロバート・エドラー合唱音楽賞」をアジア人で初めて受賞した。 現在、ヨーロッパ、アジア各国で国際合唱コンクールの審査員として、国際作曲コンクールの審査員として、また講習会の講師としても活躍中である。 最近の活動としては、2015年2月、アメリカ、ユタ州ソルトレイクシティで行われたアメリカ合唱指揮者協会ACDA主催の国際合唱カンファレンスに合唱団とともに招待され、その演奏は好評を博し、また、作曲家セッションのパネラーとして参加した。また、2016年3月、国際バッハアカデミーシュトゥットガルトの招聘を受け、ドイツ・シュトゥットガルト音大において自作品のワークショップを行い、ザールブリュッケン室内合唱団により委嘱新作”De profundis clamavi”が世界初演された。 更に、2017年にスペイン・バルセロナで開催される国際合唱連合主催の世界合唱シンポジウムにおいて、芸術委員を務めている。 代表作品・合唱曲〈オーケストラと混声合唱のためのカンタータ 水脈速み〉〈信じる〉(NHK全国学校音楽コンクール課題曲)〈混声合唱とピアノのための やわらかいいのち〉〈女声合唱とピアノのための 三つの詩編〉他多数。他に、管弦楽のための〈De Profundis〉〈黙礼〉など。 耕友会芸術総監督。軽井沢国際合唱フェスティバル総合音楽監督。世界合唱シンポジウム2017バルセロナ芸術委員。Intercultur World Choir Council日本代表評議員。東京都合唱連盟副理事長。全日本合唱連盟東京副支部長。全日本合唱連盟国際青少年委員。日本作編曲家協会会員。日本合唱指揮者協会会員。合唱表現研究会代表。国際コダーイ協会会員。
Masa MATSUURA
桐朋学園大学音楽学部演奏学科(声楽専攻)卒業。同大学研究科(作曲専攻)、アンサンブル・ディプロマコース(ピアノ専攻)修了。パリ国立高等音楽院ピアノ伴奏科および室内楽科修了。吹田音楽コンクール(作曲部門)、奏楽堂日本歌曲コンクール(作曲部門)、日本モーツァルト音楽コンクール(ピアノ部門)などにて入賞。これまでに作曲を石島正博、金子仁美、原田敬子、ピアノを今泉紀子、大崎かおる、小澤英世、ゴールドベルク山根美代子、星野明子、J.ケルネル、声楽を名古屋木実の各氏に師事。 これまでに声楽、合唱、室内楽、伝統楽器を使った作品など様々な作品を手がけており、中でも2012年11月に仙台で初演された東日本大震災復興祈念曲「レクイエム」は、日本のみならずヨーロッパやアメリカなどでも演奏されている。そのほか代表作として、サクソフォーンとピアノのための「海の石」、合唱曲 「花の冠」、マンドリンオーケストラのための幻想曲「伝説」、 フルートオーケストラのための「灯夜」などがある。また、アンサンブルピアニストとしてベルリンフィル、フランス放送フィル首席奏者など、内外の著名演奏 家と多数共演。サクシアーナ国際サクソフォーンコンクール、浜松国際管楽器アカデミーなどで公式伴奏者も務める。Fontecより有村純親(Sax)とのアルバム「ロマンス」(レコード芸術誌特選盤)、「トロイメライ」をリリース。東京芸術大学、上田女子短期大学非常勤講師を経て、現在洗足学園音楽大学講師。
Juyoung CHOI
1997年、韓国釜山出身。現在、ソウル大学校 音楽大学 作曲科に在学中。 2017年第45回パン・ミュージック・フェスティバルに参加し、2台の散調伽耶琴(サンジョカヤグム)と杖鼓(チャング)のための作品”Gradual for 2 sanjo gayageums and a janggu”が演奏される。2021年3月にはコンサート・バンドのための作品”Hope”がコリアン・ウィンド・オーケストラによって演奏された。国防部・軍楽隊に1年9か月所属し、軍行事のために、軍歌、ポップス、民謡などの楽曲をコンサート・バンド、オーケストラ、ピアノ五重奏といったアンサンブル向けに編曲した経験をもつ。
Takatomi NOBUNAGA
1994年上智大学文学部教育学科卒業。1994・95・99年朝日作曲賞(合唱曲)、1998年奏楽堂日本歌曲コンクール作曲部門第1位、2000年現音作曲新人賞入選(室内楽曲)、2001年日本音楽コンクール作曲部門(室内楽曲)第2位などを受賞。多数の合唱曲のほかに、オペラ、歌曲、器楽作品など多岐にわたる。主な作品に《新しい歌》(合唱)、《Fragments 〜特攻隊戦死者の手記による〜》(独唱/合唱)、《マリンバ協奏曲 混線するドルフィン・ソナー》、《オペラ 山と海猫》(まつもと市民オペラ委嘱、加藤直台本・演出、佐川吉男音楽賞奨励賞)、《オペラ ルドルフとイッパイアッテナ》(オペラシアターこんにゃく座委嘱、いずみ凜台本、立山ひろみ演出)などがある。
Miho FUJISHIMA
札幌市出身。2011年北海道大学文学部卒業。 北海道札幌北高等学校で合唱を始め、これまで多くの演奏会等で歌い手、ピアニストとして活動。 2008年より混声合唱団THE GOUGEの代表を務める。作曲は独学。 これまでに明治大学グリークラブ、合唱団あべ犬北などから委嘱を受け、作曲・編曲を数多く手がける。ピアノを岡本千佳子氏に師事。
Michiko MATSUOKA
東京都杉並区生まれ。東京藝術大学作曲科卒業。ドイツ、デュッセルドルフ音楽大学に留学。これまでに作曲を長谷川良夫、南弘明、北村昭、甲斐説宗、近藤圭、ギュンター・ベッカーに師事。 東京藝術大学音楽学部作曲科非常勤講師(作曲科研究室助手)、徳島文理大学音楽学部非常勤講師、徳島県立名西高等学校非常勤講師、香川大学特命准教授、鳴門教育大学嘱託講師などを歴任。 第30回徳島県芸術祭最優秀賞受賞、第7回東京国際室内楽作曲コンクール入賞、第14回奏楽堂歌曲作曲コンクール入選。作品は日本の他、ヨーロッパ各地の音楽祭などで演奏されている。「松岡貴史&みち子作品展」を東京・徳島・ハンブルグで9回開催。 日本現代音楽協会、日本作曲家協議会会員。 公式HP 作曲家 松岡貴史・松岡みち子の部屋 https://www.takashimichiko.com [主要声楽作品] ・《砂に残った足あと》 (トランペット、ソプラノ、ピアノ) ・5つのうた《秋が触っていったから》 (ソプラノ、ピアノ) (メゾ、アルト版もあり) ・《智恵子抄》(全10曲) (ソプラノ、ピアノ)(メゾ、アルト版もあり) ・「みんなをすきに」金子みすゞの詩による女声合唱組曲 ・現代の新しい子どもの歌「朝」「わたしはわたし」(ソプラノ、ピアノ) ・「わがよろこびの頌歌は消えず」 八木重吉の詩による混声合唱組曲(アカペラ混声合唱) ・“MORI” (Alto, Flute) ・中学生の詩による2つの歌「青春」「たんぽぽ」(メゾソプラノ、フルート、サックス) ・「ひとり林に・・・」立原道造の詩による(バリトン、ピアノ) ・「見知らぬ国のうた」全3曲 (アルトソロ) ・「うみとなみ」工藤直子の詩による女声合唱組曲 [主要器楽作品] ・「青い空のむこうに」 (Flute, Violin, Piano) ・“KA-MI-E” ヴァイオリンソロのための ・「砕けたる悔いし心」 (Organ) ・“CAROL” 2本のフルートとオーケストラのための ・「闇はこれに打ち勝たなかった」ハープソロのための ・「秋の雨」(Clarinet, Violin) ・「竹」~萩原朔太郎の詩に寄せて~ (Clarinet, Cello) ・“Genesis ” 小さなオーケストラのために ・“der Weg”~「砂に残った足あと」に寄せて (BassCl. Accordion, Violin, Cello) ・「星が見ている」 (Flute, Clarinet) ・“Genesis Ⅱ Noah”(ウインドウオーケストラ)
Noboru KITAGAWA
1983年、神戸生まれ。兵庫県立長田高等学校を経て、大阪音楽大学音楽学部作曲学科作曲専攻卒業。同大学院音楽研究科作曲研究室修了。作曲を下村正彦、千原英喜の各氏に師事。 男声合唱曲「またある夜に」が平成27年度全日本合唱コンクール課題曲に採用。TBS系ドラマ「表参道高校合唱部!」最終回のエンディングで、代表作「ここから始まる」の演奏シーンが放映され、大きな反響を呼んだ。 作曲活動の傍ら、合唱講習会講師、コンクール審査員等として全国各地に招聘されている。また、自作品を中心に合唱指揮の分野でも活動の幅を広げている。 新潟アジア文化祭Asian Youth Choir 2004のオーディションに合格、テノールメンバーとして参加。2002~2010年、ジャパンユース合唱団で合唱の研鑽を積む。 コーラスめっせ幹事、Ensemble Spirandi指揮者、エントアール副指揮者、Ensemble Radiance主宰。淀川混声合唱団、なにわコラリアーズ所属。